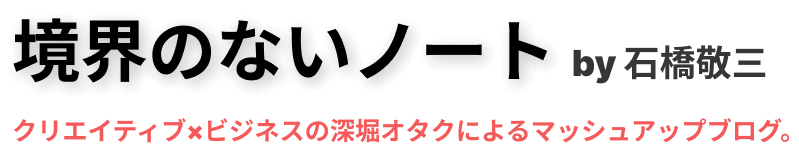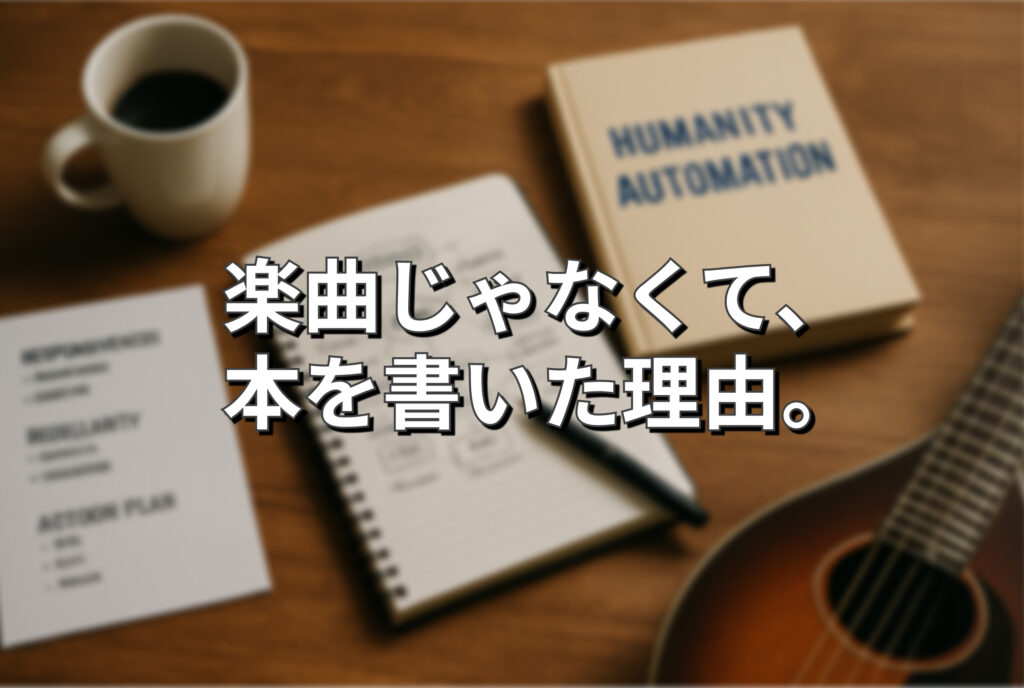AIが業務を効率化してくれる時代になりました。
文章の要約、資料作成、データ整理など、日々のデスクワークにAIを活用している人は多いでしょう。特に、ChatGPTやGeminiのようなツールを使って「これまでより短時間で見栄えの良い資料を作れる」と実感している人も多いはずです。
しかし、ここで考えてみてください。本当に業務は効率化されているのでしょうか? 個人レベルでは確かに手間が省けているかもしれません。しかし、それがチームや組織、社会全体の効率につながっているとは限りません。むしろ、AIの活用によって逆に非効率を生み出している場面もあるのではないでしょうか?
AIが作る「衣だらけの海老天」
AIを活用する場面の代表例として、資料作成があります。特に社内ミーティング用の資料作成は、AIによって格段に楽になりました。数年前までは、最低限の箇条書きだけでミーティングに臨んでいたのに、今ではAIが自動的にスライドを作成し、グラフや装飾を加えた「立派な」資料が簡単に作れるようになりました。
一見、これは効率化の恩恵に思えます。しかし、問題はその資料を受け取る側がいることです。
AIは見栄えの良い「海老天の衣」を作るのが得意です。素材が貧相であっても、たっぷりとした衣をつけることで、あたかもボリュームのある海老天のように見せることができます。それと同じように、AIが作る資料は本来シンプルに伝えられる内容でも、装飾や補足情報が増え、余計にボリューミーになりがちです。
そして人間の心理として、「見栄えの良い資料=仕事ができる」という錯覚に陥りやすいのも厄介なポイントです。「これだけ作り込んだ資料だから説得力がある」と思い込み、むしろ議論の本質を見失うことすらあります。
天ぷらの衣は消化に悪い
ここで考えたいのは、資料を受け取る側のコストです。
ボリュームのある資料を受け取った側は、まずその内容を理解するための時間を取らなければなりません。しかし、多くの場合、会議の場で「この資料、結局何が言いたいの?」という疑問が飛び交い、最終的には「本当に必要な情報」を抜き出して再整理することになります。
つまり、AIが資料作成を効率化したことで、「情報の整理」にかかる時間が会議の場で発生してしまい、結果としてチーム全体では非効率になっているのです。これはまさに、AIが生み出した「海老天の衣」の弊害と言えるでしょう。
本質(海老)を見失わないために
さらに問題なのは、そもそもの「海老」すらAIに任せてしまっている人が増えていることです。
AIは肉付け(衣をつけること)はとても上手ですが、本質(海老)を考えることは本来であれば守備範囲外です。楽だからといって「AIが出した結論をそのまま採用する(あるいはAIが出した選択肢から選ぶ)」という姿勢になってしまうと、人間が思考を放棄することになります。
そうなると、「本当に重要な情報は何か?」を考える機会を失い、結果としてAIに仕事を奪われる未来がスペースシャトルのような速度で近づいてくることになるでしょう。
だからこそ、まずは 「本質(海老)」を自分の力で見極めること を意識しないといけません。そのうえで、衣をつけるべき場面、つけるべきでない場面を判断し、適切にAIを活用することが重要なのではないでしょうか?
AIの揚げる天ぷらに惑わされないために
ChatGPTやGeminiといったAIは、非常に便利なツールです。しかし、知らず知らずのうちに非効率を生み出していることもあります。特に、個人レベルでの効率化が、チームや組織レベルでの非効率につながるケースには注意が必要です。
ここで大切なのは、以下の2点です。
- 本質を考えることをAIに任せてはいけない。
どれだけ便利でも、思考のプロセスを放棄してしまうと、人間としての価値が損なわれます。 - 本当にチームや社会のためになるかを考えてAIを活用する。
自分が楽になることだけを考えるのではなく、そのアウトプットが周囲にどのような影響を与えるのかを意識することが大切です。
AIが生み出す「海老天の衣」に惑わされず、本当に価値のある情報を見極め、自分の意志でそれを発信すること。それが、AI時代を生き抜くための鍵になるのではないでしょうか?
長文にお付き合いいただきありがとうございます。
今回のトピックに関連する記事として、以下もご覧ください。