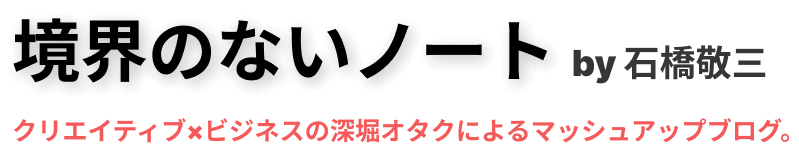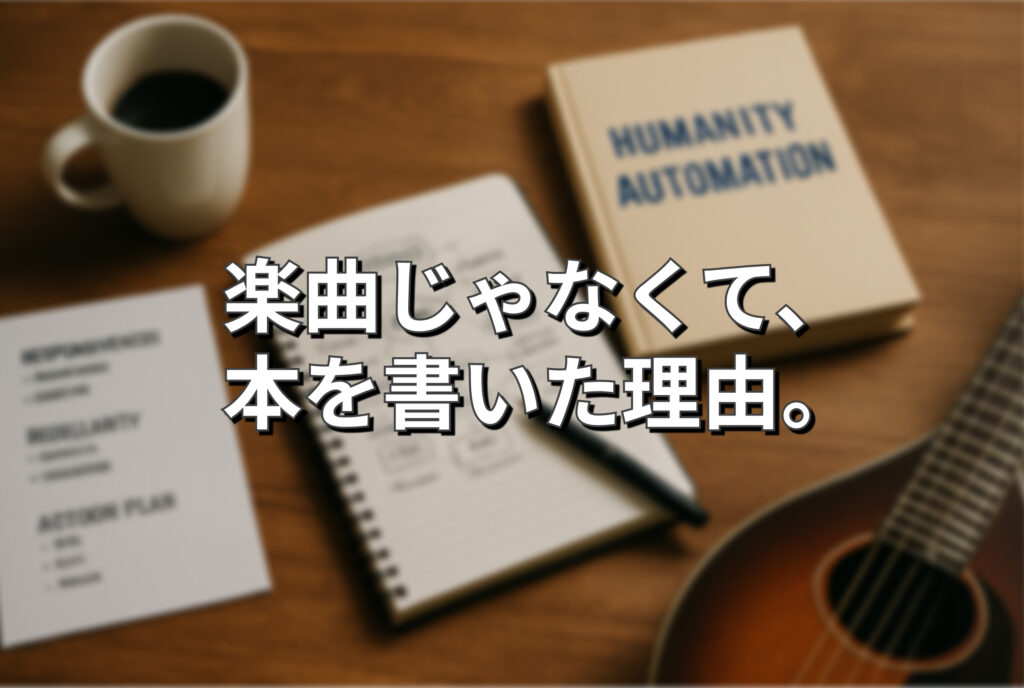こんにちは。石橋敬三です。
ブログを読むのは久しぶりという方も、たまたま今回の記事が目に入ったという方も、ようこそいらっしゃいました。
今回はちょっとしたご報告を兼ねて、最近の活動について書いてみたいと思います。
実はここ2カ月ほどで、私は2冊の書籍を出版しました。タイトルは、
どちらもAmazonのKindleストアにて、電子書籍とペーパーバックの両方でリリースしています。
ありがたいことに、いくつかのカテゴリでランキング1位も獲得しました(もちろん、ニッチなジャンルでの一時的なものですが…)。

さて、このブログを以前から読んでくださっている方や、私を「マンドリン奏者・作曲家」として認識してくださっていた方からすれば、きっとこう思ったはずです。
「え、なんで本? 音楽じゃないの?」
たしかに、自分でもちょっと不思議な感じがしています。
ただ、少しでも私と深く話をしたことがある人なら、「あぁ、たしかにそれも石橋っぽいな」と思ってもらえるかもしれません。
今日は、「なぜ本を出したのか」という話とともに、自分にとっての「表現とは何か」、そして「AIとの関係性」まで含めて、じっくりと綴ってみたいと思います。
書いた2冊の本について
最初に、それぞれの本がどういうものなのか、簡単に紹介しておきます。
『即レスするだけで すべてが上手くいく』
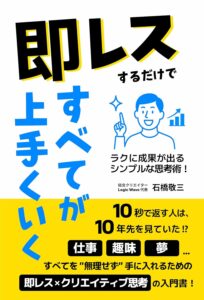
こちらは、「即レス」と「クリエイティブ思考」という二刀流をテーマにした、シンプルだけど実践的な思考術の入門書です。
-
即レス=思考の無駄を減らし、行動を高速化する技術
-
クリエイティブ=自分らしいアウトプットや解釈を生む力
この2つを組み合わせることで、「迷って動けない時間」を減らし、もっと自分の時間を自由にデザインできるようになる——そんな願いを込めて書きました。
「考えることをやめる」ではなく、「大事なことを考えるための余白をつくろう」というのが本書の本質です。
『量産される人間性』
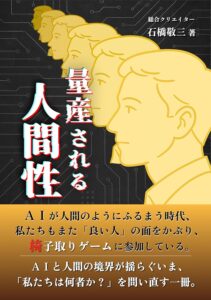
こちらはだいぶ毛色が変わって、「人間性とは何か?」というテーマをAI時代の視点から掘り下げていく一冊です。
-
AIが「人間らしさ」を模倣できるようになった今、
-
私たちは「人間性」や「自分らしさ」を、どのように定義すればよいのか?
-
社会やSNS、自己演出に満ちた現代で「本物の自分」とは何か?
-
「何者かになりたい」という願望の正体は何か?
問いのスケールとしては大きいですが、思考実験としても楽しめる内容になっています。
前者の『即レス』が「納得」や「すっきり感」を提供する入門書だとすれば、後者の『量産される人間性』は、あえて「混乱」や「問い」を読者に投げかける本です。
この2冊は、まったく毛色が違うように見えますが、実は私の中では同じ軸から生まれています。
それは、「すべての人間(自分自身も含む)を対象とした観察」が起点になっているということです。
作用としては対極的な2冊ですが、どちらも【人間へのエール】という位置づけになっています。
なぜ、本だったのか?
「音楽をやっていた人が、なぜ突然、本を?」
これは多くの人に尋ねられたことです。
でも実のところ、私自身の感覚としては「突然」ではないんです。
昔から、音楽に限らず、いろんなことを考えては形にするのが好きでした。
良い作品からエッセンスを抽出して学び、それを最構成し、自分なりのこだわりをもって形にする。
そして、その中心には、いつも「言いたいこと」がある。
それは、音楽を作るときも、動画を作るときも、CDジャケットのデザインをするときも、ブログを書く時も同じでした。
何かを「表現したい」という衝動があるとき、それが音楽なのか、本なのか、デザインなのか、私の中ではどれも同じライン上にあります。
つまり、アウトプットの形式は違えど、「内側から湧き出てくる何かを外に出す」という点ではすべて共通しているわけです。
ただ、今回はあえて「言葉」という手段、そして「本」という媒体を使うことに挑戦してみました。
音楽は抽象的な表現ですが、言葉はもっと直接的です。
聞き手(読み手)との距離も、少し違います。
だからこそ、「今の自分の考えや問い」を、もっとストレートに伝えてみたい。
それが、本というフォーマットを選んだ理由です。
表現とは、「何を言うか」と「どう言うか」
少し話が抽象的になりますが、表現には大きく2つの軸があると考えています。
-
何を言うか(What to say)
-
どう言うか(How to say)
音楽は「何を言うか」も大事ですが、「どう言うか」の領域がとても広く、解釈も自由度が高いメディアです。
一方、本(とくにエッセイや実用書)は、「何を言うか」に特に比重がかかります。
もちろん、書き方や語り口にも工夫は必要ですが、「この本でいったい何を伝えたいのか?」という核心が、読者に伝わらなければ意味がありません。
今回、本という形に向き合ったことで、自分の中の「何を言うか」という軸と、改めて真剣に向き合うことになりました。
しかも、今はChatGPTのような生成AIも使える時代です。
言葉で何かを作ること、つまり「どう言うか」のハードルが、ぐっと下がっているわけです。
だからこそ、私たち人間にとっては、「何を言うか」「何をしたいのか」の自由度が上がるとともに、その責任が増していると考えています。
生成AIとどう向き合ったか
実を言うと、最初の本『即レスするだけで~』では、生成AIを活用した執筆の実験もしてみました。
「この本のテーマと要旨はこうです。これをもとに、章構成や導入文を考えてみてください」
こんな具合に、AIに指示を出してみたわけですが、結論、うまくいきませんでした。
AIから出てくるアイデアは、すべて私が渡した情報や世間の常識の範囲に収まるもので、何も面白く感じないのです。
確かによくまとまっていて、フォーマットは美しいです。
「どう言うか」の部分に関しては、満点に近いでしょう。
しかし、「何を言うか」「その背景にある視点」までは、AIには難しいようでした。
「あぁ、自分で考える前にAIの意見を聞いちゃうと、何も面白くないものが出来てしまいそうだ」
途中でそう感じたため、いったんAIにサヨナラを言って自分だけで企画を進行するようになりました。
AIは、要素をうまく収束させることには長けています。
でも、関係のなさそうなアイデア同士を掛け合わせて、新しい文脈を生み出すような「飛躍的発想」は、まだまだ人間の専売特許のようです。
正直、少し安心しました。
もしこの部分までAIが担えるようになったら、本気で「人間って何のためにいるんだっけ?」と考えなければいけないところでしたので。
書いてみて「本は対話だ」とわかった
本を書くというのは、思っていた以上に「対話」なんだと感じました。
自分自身との対話でもあり、未来の読者との対話でもある。
ときに筆(タイピング)が止まり、「これは本当に伝わるだろうか?」「そもそも本当に言いたいのは?」と悩む時間もある。
でもその時間は、時が止まっているというものではなく、そこには確かに「対話」を感じるのです。
執筆を進めるにつれ、自分自身の考えが深まっていく喜びがありました。
音楽では「響き」や「空気」で伝えていた部分を、今回は「言葉」で伝える。
その難しさと同時に、その面白さも、思い切り味わうことができました。
…というわけで、本を2冊書きました。
どちらも、自分の中の問いと向き合い、じっくりと手を動かして書いたものです。
-
何かに挑戦したいけど、迷ってばかりいる人
-
SNSやAI時代に「自分らしさって何だろう」と立ち止まってしまった人
-
自分の思考や行動に、少しでも手ごたえを感じたい人
そんな方々に、読んでいただけたら嬉しいです。
▶ Amazon、Kindleストアで公開中です
『即レスするだけで すべてが上手くいく』 : 【図解&チャート付】悩みゼロで動けるシンプルな思考術
『量産される人間性』 : 【AIと人間の境界】が揺らぐ今、「私たちは何者か」を見つめ直す一冊。
最後までお読みいただきありがとうございました。
もし読んでみて「ちょっと面白かった」「考えるきっかけになった」と思っていただけたなら、レビューなどもぜひお寄せください。
これからも、音楽に限らず、表現というフィールドで自由に遊んでいけたらと思います。
どうぞ、これからもよろしくお願いします。