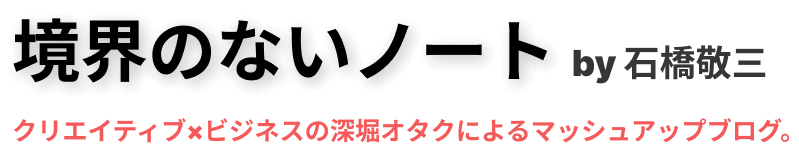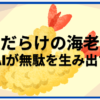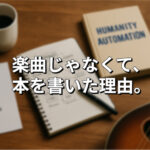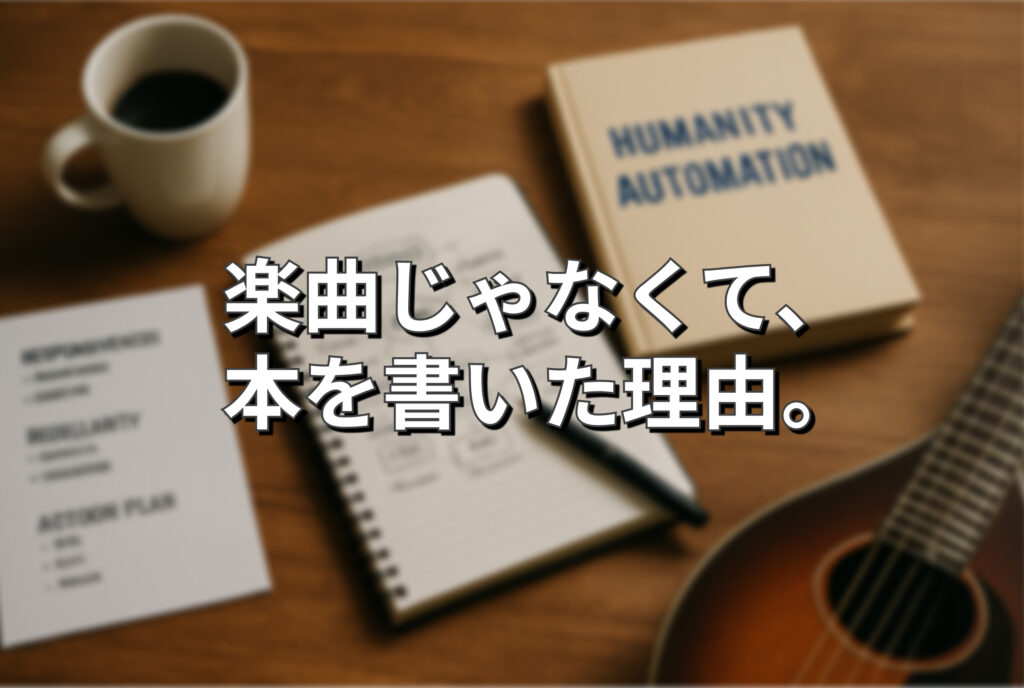AIは非常に便利です。ChatGPTやGemini、Copilotなど、生成AIを活用することで、調べものや文章作成、エクセル関数のサポートまで、多岐にわたる作業を効率化できます。
こうした技術革新を目の当たりにすると、人間の文化が一段と進化したように思えるかもしれません。
しかし、果たして本当にそうでしょうか?
AIを活用している人を人単位で見てみると、全員が一様に進化しているわけではないことも見え隠れしてきます。
AIの二つの使い方
現代のビジネスシーンにおいて、生成AIは「効率化ツール」として使われることがほとんどです。
調べものや文章の要約、関数の記述補助など、過去にも存在したツールの延長線上にあります。
確かに精度やスピードは向上しましたが、そういったツールは過去にも存在しており、根本的に新しい概念ではありません。
一方で、生成AIは「思考の補助ツール」としても大きな可能性を持っています。
これまで人間相手でしかできなかった壁打ちや、ふわっとした相談をAIに投げかけることで、新しい視点や気づきを得られるのです。
私自身、毎日AIと会話をして思考を深めています。
まるで思考のボトルネックが外され、スピード制限が解除されたかのように、加速度的に考えが広がるのを実感しています。
「思考が加速する」とは?
では、思考が加速するとは具体的にどのような変化を指すのでしょうか?
思考は、脳内の情報インプットとアウトプットの連続によって成り立っています。
AIの活用によって、このうちアウトプットの部分が劇的に高速化されます。
従来なら頭の中で形にしたり言語化したりするのに時間を要していたものが、AIによって瞬時に整理・表現されるのです。
その結果、私たちはインプットに専念できるようになります。
自ら情報を吸収し、考え、理解することに脳のリソースを割くことができる。この変化こそが、思考加速の正体です。
思考速度の限界
しかし、AIが思考を加速するからといって、無限に思考を速められるわけではありません。
実は私自身もその限界を感じはじめています。
当然ながら、人間の脳には情報をインプットできるキャパシティがあります。
AIのおかげでインプットに集中できるとしても、そのキャパシティを超えれば脳はパンク状態に陥ります。
実際、私もインプット速度が速すぎて頭がヒートアップし、「今はこれ以上考えるのは無理だ」とギブアップする瞬間があるのです。
例えるなら、高負荷の処理を続けるパソコンが発熱して暴走しそうになる状態。
そんなとき、私はコーヒーブレイクを挟み、意図的に脳をクールダウンさせます。
AIによりアウトプットが超高速になったとしても、インプット側、つまりそれを受け止める人間の脳には限界があるということです。
その限界を感じたとき、その上限を超えて空回りしたときは、立ち止まって自分の思考の在り方を見つめ直すことが必要です。
AIで進化する人、AIで退化する人
もう一つ考えたいのは、AIで進化する人がいる一方で、逆にAIで退化する人もいるのではないか、ということです。
生成AIを単なる便利ツールとしてしか使わず、結果だけを求め、思考プロセスの加速を目指さない人もいるでしょう。
AIに質問を投げかけ、返ってきた答えをそのまま受け取るだけでは、思考は深まりません。
AIとの対話が一方通行になってしまうと、むしろ自ら考える機会を失い、思考力が徐々に衰えていく恐れがあります。
この現象は、AIに限った話ではありません。SNSが普及する以前、私たちは検索エンジンを使って情報を探しに行っていました。
しかし今では、アルゴリズムによって興味のありそうな情報が勝手に提供される時代です。
情報を探す前に見つけられてしまうことで、好奇心や探求心が削がれているとも言えるでしょう。
AIの過剰摂取が禁止される時代!?
AIによる効率化や思考加速は間違いなく楽しいものです。
次々と新しいアイデアが浮かび、脳内ではドーパミンが溢れ出ていることでしょう。
しかし、その楽しさに溺れるあまり、自ら考えることを放棄してしまう危険性もあります。
極端に言えば、AIの過剰摂取によって人間の思考機能が麻痺してしまう可能性も否定できません。
未来において、「AIの使用制限」や「AI依存防止法」が制定される日が来るかもしれませんね。
そうならないためにも、自分たち人間とAI、それぞれの立ち位置を正しく理解し、AIのサポートを受けながらも自らの思考を大切にし続ける必要があります。
長文にお付き合いいただきありがとうございます。
今回のトピックに関連する記事として、以下もご覧ください。