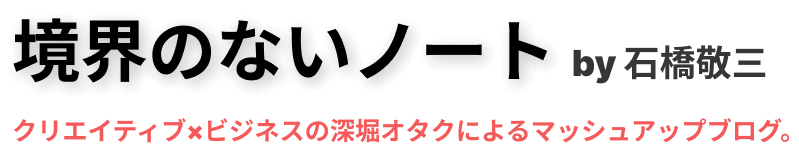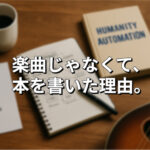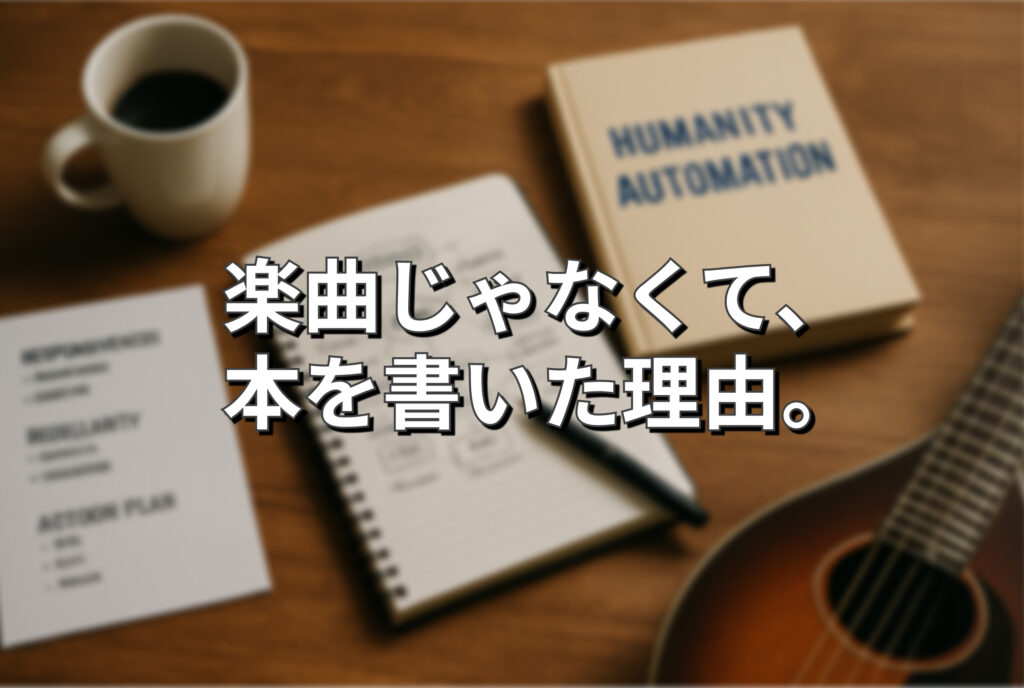初めまして。あるいは、お久しぶりです。
私は元々マンドリンの演奏や作曲を生業にしていましたが、その後「体験づくり」を得意とするマーケッターに転身し、最近ではLogic Waveというメーカーを立ち上げ、楽器演奏に関する新しい発明品を世に送り出すことをライフワークにしています。
2022年には「natu-reverb」、2023年には「Sitar Express」、2024年には「ピックの達人(The Pick Master)」と、ほぼ1年に1つのペースで発明品をリリースしてきました。
ありがたいことに、どのプロダクトも大好評で、最初のnatu-reverbはリリースから3年経ちましたが、それでも反響がまだまだ広がっている感触があります。
それと、「ピックの達人」について、最近とても嬉しい話を聞きました。
このプロダクトは元々、ピックが空中に固定されてズレない、そしてピックでの演奏とフィンガーピッキングをスムーズに切り替えられる、というコンセプトで作ったものです。
それが、どうやら、事故などで指を欠損された方がギターを演奏する際に便利だと話題になっているようなのです。
毎日ギター演奏を楽しんでいた方が、ある日、事故で指を失い、ギター演奏が難しくなる。そんな状況でお役に立てているとしたら、こんな嬉しいことはないです。
思えば、作曲でも同じような経験がありました。
自分が作った楽曲が、自分の想定していない表現で演奏されたとき、自分の脳内が新しい世界とコネクトするような感覚があります。
自分の頭の中の世界をアウトプットしたはずなのに、それを受けた人の新鮮な解釈が逆輸入されて、脳内に新鮮な風が吹くイメージです。
静かでクリエイティブな意識交換とでもいうべきでしょうか。
発明品を通じても、このような体験ができるとは思っていませんでした。
さて、そんな体験からもインスピレーションを得た私は、2025年、新しいデバイスを発明する運びとなりました。
すでにティザー的に動画をいくつかアップロードしていますが、その新しいデバイスとは、ギターを擦弦楽器のように演奏できるようにするアタッチメントです。
まだ発売前なので詳細は控えますが、このデバイスについて少しお話したいと思います。
動画へのコメントで既にあるとおり、これはハーディガーディ [hurdy-gurdy] という中世ヨーロッパに生まれた楽器からヒントを得ています。
ハーディガーディは、大きな木の円盤で弦を擦って音を出す楽器で、「ハンドルを回す」というギミックがとても魅力的です。
しかし思えば「ハンドルを回す」という体験は、現代ではどんどん失われていると思いませんか?
昔は、車の窓を開けるときや何か機械を動かすとき、ハンドルを回すのが当たり前でした。
ですが、現代人である私たちは、ハンドルを回すという行動を一日のうち何回とるでしょうか?
例えば、現代の生活スタイルでも、一息いれるときに、ミルのハンドルを回してコーヒー豆を挽くという人がいます。
ハンドルを回すという体験は、懐かしく、でもどこか新鮮な風を吹き込んでくれるような印象があります。
ひょっとして、ギターの演奏に「ハンドルを回す」という体験を組み合わせ、そしてバイオリンのような音が出せたら面白いんじゃないか。
そう考えた私は、ハーディガーディの仕組みを応用して、新しいギターアタッチメントを考案しようとしたわけです。
さて、いつもそうなのですが、何かを思い付くことと、それを実現することの間には、ヒマラヤ山脈よりも高く厚い壁があります。
当然、円盤を弦に擦りつけるだけでは、全くうまく機能しません。
実用化までには無数のハードルを越え、いくつかのエポックメイキングなアイデアが必要でした。
今回も、大量の試作品(ダンボール箱3つ分)を作り、トライ&エラーの道を地道に歩みました。

私は、発明に挑む際にいつも心がけていることがあります。
自分の好奇心を大事にすること。
そして、小さなことを一つずつ解決することです。
まず、発明の道はとても泥臭く、モチベーションを高く保つ必要があり、その原動力として頼れるのは好奇心しかありません。
自分自身に「これは面白い」と思わせ続ける、いわば「好奇心ケア」のような意識が重要だと感じています。
そして私は、発明というプロセスの大半は、とても複雑に絡まった紐をほどいていくような作業だと思っています。
紐をほどくためには、力任せにほどこうとしてもうまくいきません。
冷静に、まずは構造を正しく理解し、一つずつ紐を外していく必要があります。
発明も同じで、うまく機能しない原因や変数を分解し、ひとつずつ丁寧に解決していくのです。
例えば、一番最初に作った試作品は、直接円盤を上から弦に当てる仕組みでした。
しかし、ギターは開放弦と押弦時では弦の高さが違うため、押弦時には円盤が弦に当たらず音が出ません。
この時点で「弦の高さという “変数” をどう扱うのか」という課題が生まれるわけです。
その課題に対して、どのような解決の切り口があるのかを思い付く限りリストアップし、一つずつ試していきます。
そんな具合に、複雑に絡み合った課題を地道に紐といていく。気づけば試作品の屍が山を築いているといった状況です。
長くなりましたが、この 「#回して演奏するギター」という体験をお届けできることをとてもうれしく思います。
既に動画にもたくさんの方から「どこで手に入るんだ?」とのコメントをたくさんいただいていますが、あともうしばらくお待ちください。
何しろ全く新しい体験の提供になるため、リリースまでに多くの準備が必要です。
といってもあともう少しです。引き続きご期待ください。
以下は2025年7月12日の追記です。
すでに動画の説明欄にも記載していますが、Cantareelの商品ページやチュートリアルのページが完成しております。
誰も見たことのない楽器アタッチメントのため、十分な説明やチュートリアルが必要だと考えたため、事前に多くの準備をしていました。
チュートリアルのページには、取り付け方の解説動画だけでなく、チューニング例や指板チャート、無料楽譜などを用意しています。
さて、動画へのコメントでたくさんご質問をいただいており、ここでいくつかお答えしたいと思います。
これはいったい何だ?
ダントツで多かったのはこのご質問です。(当然ですが…)
これは、Cantareelといって、私が考案し、開発したものです。
名称の由来は、Cantare(イタリア語で「歌う」の意味)とReel(昔のビデオやカセットなどでテープを巻く装置)の組み合わせです。
Cantareelをギターに取り付け、ハンドルでホイールを回すと、ホイールに連動して2本ループが動きます。
その2本のループが弦を振動させ、バイオリンやバグパイプのような持続音を出します。
どうやって思い付いたんだ?
私はあまり多くの友人を持っていませんが、それでもいつもインスピレーションをくれる友人たちがいます。
彼らは私の音楽仲間ですが、お互い、今は別の分野でも挑戦を続けています。
今回のCantareelの開発を始めたのは、彼らと楽しい時間を過ごした直後のことでした。
日々を生きていると、どうしても、現状の世界や物事にうまく合わせることを考えがちです。
しかし、彼らと会うと、なぜか固定観念がやわらぎ、「現実」ではなく「理想」に意識を持っていくことができるのです。
思えば、私が3年前に特許を取ったnatu-reverbの開発をはじめたのも、彼らと会った直後でした。
ナイロン弦ギターやエレキギターに対応する?
ナイロン弦にも問題なく対応します。
エレキギターは形状が様々ですので、「対応します」とは言えません。
ただ、実際は多くのエレキギターに対応すると思います。
弦がすぐにダメになるんじゃない?
この質問が多いことは予想していなかったので、少々驚いています。
まず、Cantareelの演奏時は、硬いホイールで直接弦を擦るものではなく、柔軟性のあるループで弦を擦る形になっています。
物理的な摩耗ということに関しては、むしろ爪やピックで演奏するよりも、弦の負担は少ないです。
ただし、弦に付着した松脂を放置すると固まってしまうこともあるので、演奏後は松脂をこまめに拭いたほうが良いと思います。
ホイールを二つにしないのか?
もちろん試しました。
ホイール2つのパターンだけでなく、メインホイール1つ+サブホイール2つのパターンなど、いくつかテストしました。
しかし、ループにたわみが生じやすくなり、回転が安定したとしても、音はかえって不安定になります。
また、順回しと逆回しで音の差が激しくなってしまいます。
結果、デメリットのほうが大きいため、ホイール1つのパターンがベストだと判断しました。
6弦と1弦がもったいなくないか?
開発の中盤では、6本全部の弦を鳴らすモデルも作っていました。
しかし、弦6本すべて鳴らすと、音が濁り、メロディも埋もれてしまいます。
例えば、きれいな澄んだ色の絵具があったとして、混ぜる色が多ければ多いほど、その色は黒に近づいていきます。
多ければ多いほど良いというものではないということです。
モーターを付けて自動で回るようにしないのか?
個人的には、このコメントが多いことに驚きました。
私としては、Cantareelの核には、「手で回して操る」という体験があり、その体験には歴史が宿っていると考えます。
モーターで動かすとなると、その体験の核を失うことになります。
また、電動にするのであれば、そもそもこのような機構である必要はないと思います。
もっと効率的な方法で、同じ音が出せるはずです。ただ、個人的にはその方面にあまり魅力を感じません。
もちろん、Cantareelをモーターで動かすというアイデアを否定するわけではありませんので、気になる方はやってみてください。
どこで買える?
Cantareelの商品ページをチェックしてください。
おそらく、まだまだお答えできていない疑問がたくさんあると思います。
商品ページやチュートリアルページのFAQにも、疑問を解決するヒントがあると思いますので、一度チェックしてみてください。