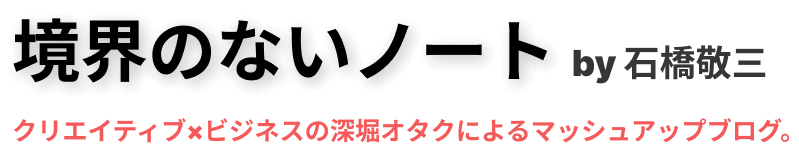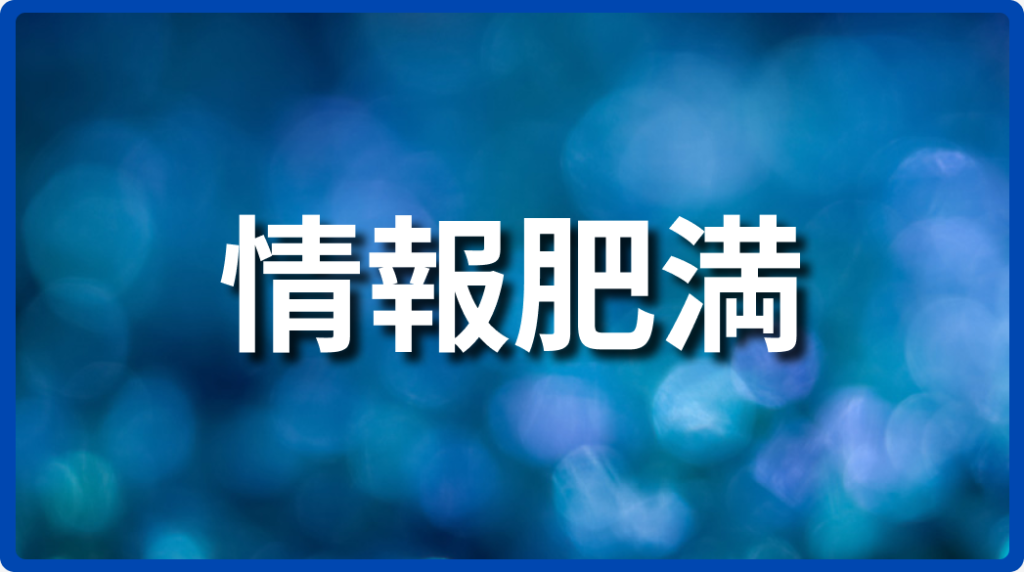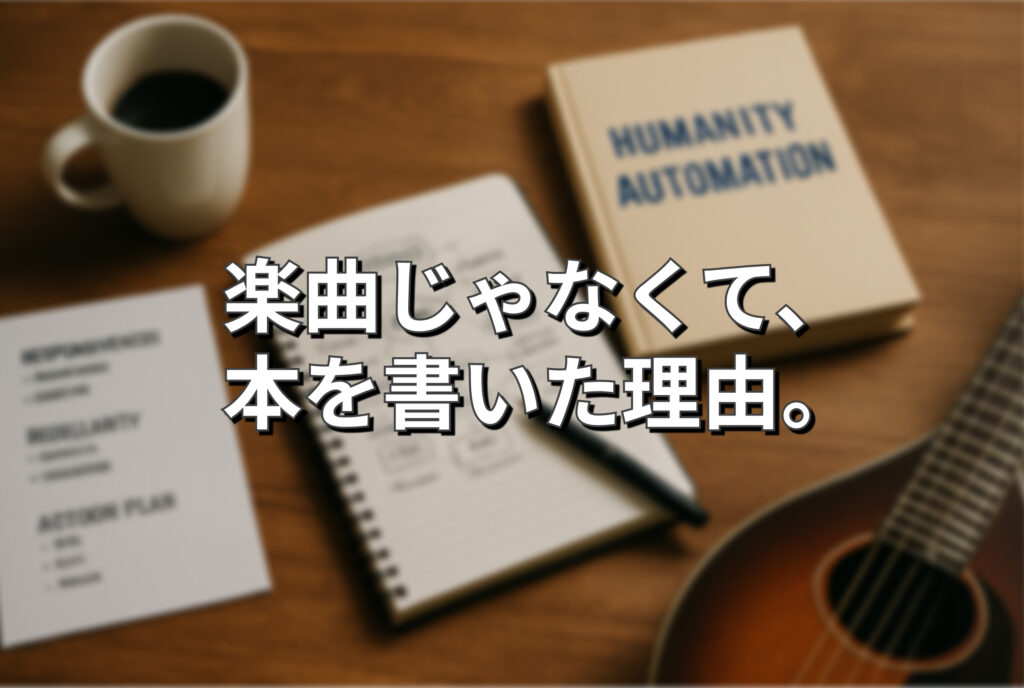現代は情報の飽食時代。
次から次へと流れ込むニュース、SNSのタイムライン、動画コンテンツ——気づけば私たちは情報を摂取しすぎているのではないでしょうか?
私はこの状態を『情報肥満』と呼んでいます。いわば、情報を過剰に摂取し、処理しきれずに思考が鈍くなってしまう状態です。
では、なぜ私たちはこんなにも情報を取り込み、どうすれば健康的に付き合えるのでしょうか?
指数関数的に増える情報量
もう10年以上前の話ですが、インターネット上の情報量は10年で600倍になっているということを聞いたことがあります。
インターネット上の情報量は、おそらく今日も指数関数的に増加していることでしょう。
個人の生活を振り返っても、この10年で明らかに情報量が増えたと感じる方は多いのではないでしょうか。
日々のニュース、ショッピング、娯楽、ライフライン、健康管理に至るまで、私たちの社会はインターネットやスマートフォンに大きく依存しています。
たしかに、20年前、10年前に比較すると、とても多くの情報が簡単に手に入るようになり、生活も便利になりました。
でも、そんなに多くの情報を手に入れてどうするのでしょうか?
そもそも、人は情報(単純な情報だけでなく抽象的な表現を含む)をインプットし、それを消化した上で何らかの形でアウトプットする生き物です。
たとえば、愛読書や憧れの芸能人などから影響を受けて、関心分野や考え方が変化したりします。
長い年月をかけて考え方や価値観に与える影響もあれば、「あれ、今日の自分って何かいつもと違う視点もってるな…昨日あの本を読んだからかな?」などという短期的、一時的な影響もあるでしょう。
さて、前提はこの辺にして、『情報肥満』の核心に踏み込んでいきましょう。
情報は、脳にとっての食べ物
私は、情報の本質は、食べ物と同じだと考えています。
人は食べ物で空腹を満たし、食べ物から得られた栄養やカロリーを消費して行動したり、自らの筋肉や臓器、骨を作ったりします。
ときには食べすぎてしまい、お腹いっぱいで動けなくなることもあるでしょう。
また、ジャンクフードばかり食べていると、良い身体を作ることもできないでしょう。
それと同じように、情報も「量」と「質」が重要です。
しかし、現代社会では、情報の量と質はとても軽視されているようです。
スマートフォンは、自分の意思に関わらず、勝手に大量の情報を見せてきます。
情報の量が増えてくる一方だし、量の増加に伴って質は下がってくる一方のように感じます。
いうならば、大盛り食べ放題のお店に毎日かかさず通っている気分です。
自分のテーブルには、続々と高カロリーで “一見” 魅力的なジャンクフードが続々と運ばれてくるため、腹八分目の意識をしっかりと持たない限り、毎日食べ過ぎてしまうのです。
私たちは、情報の量と質を意識的にコントロールしなければならない時代を生きているのではないでしょうか?
情報肥満のリスク
ジャンク情報を過剰に受け取り続けると、頭や体が重くなり、本当に大切なことが埋もれてしまい、一体何をすれば良いのか分からなくなってしまいます。
私は、情報を過剰に受け取ることを『情報過食』、そしてそれによって引き起こされる状態を『情報肥満』と呼ぶようにしています。
情報を過剰に摂取すると、次のような問題が発生します。
- 思考が散漫になる(情報が多すぎて何を優先すべきか分からなくなる)
- 決断力が鈍る(選択肢が多すぎて選べなくなる)
- アウトプットが滞る(情報を消化しきれず、自分の考えがまとまらなくなる)
日々受け取る大量の情報。
その情報は本当に受け取る必要のあるものなのでしょうか?
何も「一切の無駄をなくしてストイックに生きるべき」とは思いません。
食べたいときには、デザート(完全なる娯楽)を食べてみるのも良いでしょう。
でも、ジャンクフードで満腹になった状態では、デザートを楽しむことはできないはずです。
胃袋も脳も、余白が必要なのです。
余白のない状態で無理やり詰め込んだとしても、体や脳はうまく機能しません。
では、どうすれば『情報肥満』を防げるのでしょうか?
情報肥満を防ぐ2つのステップ
情報肥満を解消するにはどうすれば良いのでしょうか?
結論から言うと、以下の2ステップに分けて考えると良いと考えます。
- まずは量を減らす
- 質の高い情報を選ぶ
まず情報の絶対量を減らし、余白を作ることで整理整頓がしやすい環境を作ることを優先します。
余白がある程度できたら、入ってくる情報を客観的に観察し、必要に応じて処分したり入れ替えたりして質を高めます。
散らかった部屋を片付けるのと同じ流れです。
まずは量を減らす
胃袋の大きさが人によって違うのと同じように、まずは、情報量のキャパシティも人によって違うことを認識しておくと良いでしょう。
腹八分目という言葉がありますが、情報については「五分目」くらいに留めておくのが良いと考えます。
食べ物とは違い、情報は目に見えないので、脳が満腹になっていることに気づきにくいからです。
気づいたときには既に頭が一杯一杯になってしまった、何をしたら良いのかわからない…という面倒なことは防ぎたいものです。
まずは日常的に入ってくる情報の量を少なくすることが最優先です。
- SNSの使用時間を制限する
- 通知をオフにする
- 定期的に「情報断食」をしてみる(丸一日スマホやネットを見ない日を作る)
食べすぎないためには、まず適量を知ることが大切ですよね。それと同じように、自分にとって適切な情報量を把握することが重要です。
質の高い情報を選ぶ
ある程度の余白ができたら、その余白を活かして「本当に欲しい情報」をしっかりと見極めてみましょう。
といっても、余白があって余裕のある状態になっていれば、意識をしなくても自然と見極めることができるはずです。
あとは、余裕をもって、自分が求める情報を存分に味わうだけです。
- 信頼できる情報源を厳選する
- 「本当に必要な情報か?」を常に問いかける
- インプットだけでなくアウトプットも意識する(得た情報を人に話したり、文章にまとめる)
質の高い情報をきちんと消化できるだけ取得(インプット)する。
これが、健康的で良いアウトプットを出すコツなのではないか、と考えます。
情報の余白を作ろう
何も「無駄な情報をすべて排除するべき」と言いたいわけではありません。
たまにはジャンクなお菓子を食べるときと同じような、一瞬の幸福感を味わうのも良いでしょう。
ただし、ジャンク情報でお腹いっぱいになった状態では、本当に必要な情報を取り込めなくなり、良いアウトプットもできません。
食事と同じく、情報にも「余白」が必要です。
脳が満腹になりすぎないよう、自分に合った情報の取り方を見つけてみてください。
長文にお付き合いいただきありがとうございます。
今回のトピックに関連する記事として、以下もご覧ください。